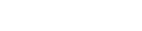マシニングセンターによる製作方法では、削れる材質であれば全て加工対象となり得ます。しかし、塊から削り出すため、加工した際に排出される切削粉は廃プラスチックとして処理することになります。また、複雑な形状の場合は加工方向を変えるなどの手間が発生し、形状によっては加工できない箇所も検出されてしまいます。
3Dプリンター市場において注目される「ペレット材」とは
今まで使いたくても使えなかった材質による造形品がその手に

近年、3Dプリンター市場において、従来のフィラメント材ではなく、ペレット材の使用が注目されています。その背景には、コスト、造形速度、材料自由度、環境への配慮、大型造形への適性など、さまざまな面で優位性を持っているからです。
試作品 作り方の比較
製品市場投入前に同一材料で試作品製作を行う場合、次のような方法が考えられますが、それぞれ一長一短が存在します。
マシニングセンターで加工する(直彫り)

試作金型を用いた射出成形
金型を用いて試作を行う場合、量産品と同じ樹脂を用いることができるため、量産と同じ性質で各種検証を行えます。その反面、金型構造が複雑化すると製作コストも高額になるうえ、設計変更時の対応が難しいといった欠点があります。
3Dプリンターで製作する
3Dプリンティングを行う場合は、形状に制約もなく3Dモデルからあらゆる形状を造形できますが、使用できる樹脂が限られるといった欠点が存在します。
フィラメント材料を使った3Dプリンティングのデメリット
材料押出法と呼ばれる一般的な3Dプリンティング方式では、「FDM(Fused Deposition Modeling)」や「FFF(Fused Filament Fabrication)」と呼ばれる細長いワイヤ状の樹脂材料(フィラメント)を熱溶解しながら積層して造形します。
多くの3Dプリンターでは、各メーカーが提供するフィラメント群の中から、用途に合ったものを選択しますが、希望する物性を持つ樹脂が必ずしも用意されているとは限りません。そのような場合、近い物性の樹脂で妥協するか、造形品の用途を変更するなど、制約が生じる場合がありました。

ペレット材料とは
ペレット材料とは、主にプラスチック成形(射出成形など)で用いられる原材料で粒状形態を採用しています。大半の成形機は熱を加えて樹脂を溶かし、スクリューで練りながら金型へ送り込みます。その際、粉末状態や粒状が大きすぎるとスクリューでうまく送ることができず成形不良につながります。そのため、多くのペレット材料は3~5mm程度のサイズで用意されています。

3Dプリンターでペレット材を使用するメリット
古くからペレット材料を用いる3Dプリンティング技術の開発が進められていましたが、汎用ペレットではなく、専用材料が主で実用的ではありませんでした。しかし、ここ数年で技術も進み、汎用ペレット材料が使える3Dプリンターが市場に投入されています。
3Dプリンターでペレット材を使用する際のメリットを考えてみましょう。
コスト削減
通常フィラメントよりも安価なため、材料コストを抑えながら3Dプリントを行えます。
素材の選択肢
幅広い種類のプラスチックに対応しているため、異なる素材を組み合わせてオリジナルの材料を作成することもできます。
| 汎用プラスチック | PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)、PS(ポリスチレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、ABS(アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン樹脂)など |
|---|---|
| エンジニアリングプラスチック | PC(ポリカーボネート)、POM(ポリアセタール)、PA(ポリアミド)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)など |
実製品に近い造形ができる
多くのプラスチック製品は、ペレット材料を用いて射出成形機などの機械で大量生産されています。市場には豊富な種類のペレットがそろっており、試作品やオリジナルパーツ、補修部品など、さまざまな用途に活用されています。
環境への配慮
一般的なフィラメント材料よりも環境に優しい。ペレットはリサイクルされたプラスチックから作られることが多く、廃プラスチックの再利用に貢献します。また、廃プラスチックの大幅削減として、SDGs(持続可能な開発目標)に取り組む一環としてペレット材は有用です。
このように3Dプリンターでペレット材料が使えるようになると、多くのメリットが得られます。特に環境配慮においては世界規模での対策が求められており、廃プラスチックなどをリサイクルして使うことにより環境への影響を抑えられるようになります。
3Dプリントで、廃棄物を資源に変え未来を創造するモノづくり
3Dプリンター市場において注目される「ペレット材」とは
従来のフィラメント材に代わる新素材として注目を集めている「ペレット材」。コスト削減、素材自由度、環境への配慮など、さまざまな面で優位性を持つこの素材が、3Dプリンター市場にどのような変革をもたらすのでしょうか?
廃プラスチックと食物残渣問題
近年、世界的な課題として「廃プラスチック問題」と「食物残渣問題」が深刻化しています。これらの問題は、環境汚染や資源枯渇、地球温暖化など、さまざまな問題を引き起こしています。
3Dプリント技術とサステナブル素材で革新的なモノづくり―株式会社ExtraBold
地球温暖化や海洋汚染などの深刻な環境問題に対し、ExtraBoldは樹脂ペレット式3Dプリント技術とサステナブル素材を活用し、革新的なモノづくりを通して解決に貢献しています。
樹脂ペレット式の大型3Dプリンター「EXF-12」
リサイクル材で造形可能な大型3Dプリンター「EXF-12」で、環境負荷低減と資源循環型社会の実現を目指すExtraBold様。EXF-12の魅力や提供サービスについてご紹介します。