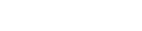FlowDesigner 製品トピックス
FlowDesignerでマンションの自然通風を解析する
FlowDesignerを用いて、南北長いマンションの換気問題を検証しました。その結果、廊下中央扉を閉じることで、多くの部屋に自然風が行き渡ることが判明しました。FlowDesignerは、目に見えない気流を可視化し、換気状況を詳細に分析できます。
FlowDesigner 快適性指標は衣替えでどのように変化するか?
FlowDesignerの快適性指標機能を用いて「衣替え」がオフィスの快適性に与える影響を検証してみましょう。着衣量が変わると快適性はどのように変化するのか、シミュレーション結果の比較を行ってみます。
FlowDesigner 2024で音響オプションの計算機能が充実!
FlowDesignerに音響オプションをご存じでしょうか? FlowDesigner 2024からは計算機能が充実し、音の解析にも対応できるようになりました。新バージョンで追加された機能や注意点を含めて解説します。
FlowDesigner 2024 新搭載のコア並列計算機能とは?
FlowDesigner 2024にコア並列計算機能が搭載されることになりました。FlowDesignerは、これまでベクトル化計算を採用してきましたが、さらなる計算スピードアップを追求し、新たな計算方法としてコア並列化を採用することになりました。
Revitで作成したCADデータをFlowDesignerにインポートする方法
FlowDesignerでBIMモデルを活用することで、構造や設備などの要素を正確に反映した気流シミュレーションを実現することができます。Autodesk RevitからFlowDesignerへのBIMデータのインポートの操作方法をご紹介します。
FlowDesigner 空調機モデルで、冷え過ぎを防ぎ、最適な室内温度をシミュレーションする
FlowDesignerの空調機モデルは、吹出温度を変化させながら冷え過ぎを防ぎ、最適な室内の温度を検証する機能です。空調機モデルの設定方法を含めて詳しく解説しています。
換気の違いをFlowDesignerで検証する(自然換気、機械換気、ハイブリッド換気)
換気は、自然換気、機械換気、ハイブリッド換気と3種類あります。中でも機械換気は、吸気、排気、または両方の方向から機械を利用するかによって、第1種から第3種までに分類されます。それぞれの特徴を知ることで、快適性やエネルギー効率の向上が期待できます。
設備設計基準の空調設計と省エネ基準の空間設計の違い
設備設計基準の空調設計と省エネ基準の空間設計は、どちらも建築物の省エネルギーを目的としていますが、そのアプローチが異なります。両者の違いを熱負荷計算の設計を例に解説します。
屋外の温度成層の作られ方をCFD風に解説
CFD解析は、温度成層などの複雑な気象現象をシミュレーションし、直感的に理解する手段として有用です。温度成層がどのように形成されるのか、そのメカニズムを「透明の箱」と「粒」で探求します。
測定でも再現できない気流・温度を人間の感覚に近づける(快適性指標)
FlowDesignerの快適性指標を利用することで、設計者やエンジニアは建築物の設計において人々の快適性を考慮した意思決定を行えるようになります。また、省エネ提案にもつながりますのでご利用ください。
VR180動画への出力に対応
VR元年とよばれた2016年以降、FlowDesigner開発プロジェクトチームでもVR対応を強化しています。2021より、ハイスペックなハードウェアがなくても、スマホなどで簡易VR体験ができる動画形式「180°動画」を出力できるようになりました。
空気齢/空気余命の絶対値出力とは
室内の空気質・換気状況を3次元で評価する場合、換気効率の指標となる「空気齢」と「空気余命」を用いると定量的に評価することができます。
換気の効果を高めるための考え方とコツ
換気はなんとなく窓を開けるだけでは不十分なことも。事業所や店舗など、人が集まる場所で効率的に換気を行うために知っておきたい、基本的な換気の考え方とコツをご紹介します。